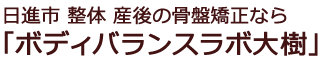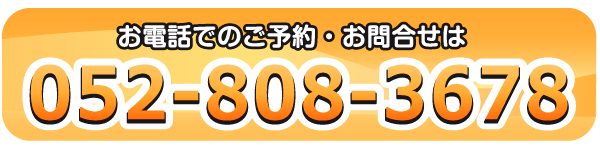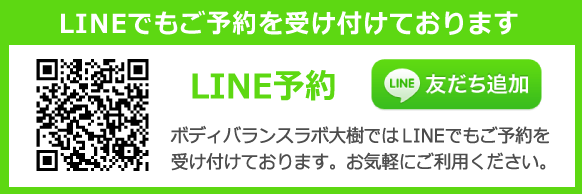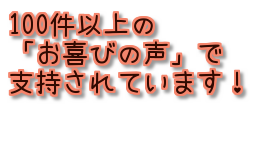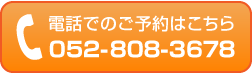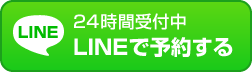日進市 タナ障害を発症
2018-08-01 [記事URL]
タナが残存している人であればタナ障害を発症することがある
膝の関節の内部には関節腔と呼ばれる空間があって、その空間は滑膜ヒダという膜のような壁によって仕切られているのです。
その中の膝蓋骨と大腿骨の間のヒダは、ちょうど物をのせる棚のように見えることから「タナ」と呼ばれています。
このタナは母体の中にいる胎児の時に、膝関節を覆う袋の関節包が作られる際に一時的にできるものです。
その為、生まれた後は退化してなくなる人とそのまま残存する人がいて、日本人の場合は残存する人と退化する人は、共に約半数ずつと言われています。
この残存したタナが関節内に挟まったり、強く刺激を受けたりすることで炎症を引き起こしてしまう疾患がタナ障害です。
通常はスポーツをしている人に多く見られる症状なのですが、タナが残存している人であれば特に運動をしていなくても発症することも少なくありません。
ちなみにタナは形状や大きさによって、太く長い状態にやや盛り上がっているA型、膜のような状態で幅が狭いB型、幅が広く厚みもあるC型、タナの一部に穴が空き縁の一部が索状に離脱しているD型の4つに分けられます。
この4つのタイプの中で、炎症を引き起こしやすいのはC型とD型で、A型とB型についてはほとんど発症することはありません。
タナ障害を引き起こす原因は、先にも触れましたが膝の曲げ伸ばしを繰り返すことにより、タナが膝蓋骨と大腿骨の間に挟まって、大腿骨の下の膨らんだ部分とこすれて炎症を起こすことです。
ですから、膝の屈伸と打撲を伴うスポーツ種目を行っている人に良くみられます。
また体質的にタナに厚みがあったり大きかったりすると、膝を酷使した状態で膝を強打したりすると症状を引き起こしてしまうこともあるのです。
特に太ももの筋肉が疲労していると筋肉が緊張しているので、タナの摩擦が強くなり症状が起こりやすくなってしまうのです。
それから、ストレッチ不足などにより筋肉が硬く緊張していると、膝蓋骨を引っ張る力が強くなってしまうことから症状を起こりやすくなります。
一生懸命スポーツに取り組んでいる10~20歳代の若い人に多く発症しますし、男性よりも女性の方が発症する割合が高いと言われています。
早い段階できちんと治療することによって、ほとんどの場合は症状が治まって、元通りスポーツをすることができるようになります。
その為にも、炎症と痛みが治まるまでは運動を休止する、超音波や温熱・冷却療法などの物理療法により膝周辺にある筋肉の緊張を和らげるということを心掛ける必要があります。
また、大腿四頭筋の柔軟性を高めるストレッチや筋肉強化をはかる筋トレを行うことも守らなくてはならないことです。
たた、先にも触れましたがタナは母親の胎内にいる時に一時的に作られるもので、特に何の機能も持たない組織なので実際には切除しても問題はないのです。
それから整体院や整骨院で骨盤・背骨の歪みを改善することで、再発しない元気な体を取り戻すことができますし、痛みの出づらい体を作ることができます。
ですから、整体院や整骨院で施術を受けるのも選択肢として検討してみるのも良いです。
日進市 タナ障害を発症なら、「ボディバランス大樹」にお任せください。